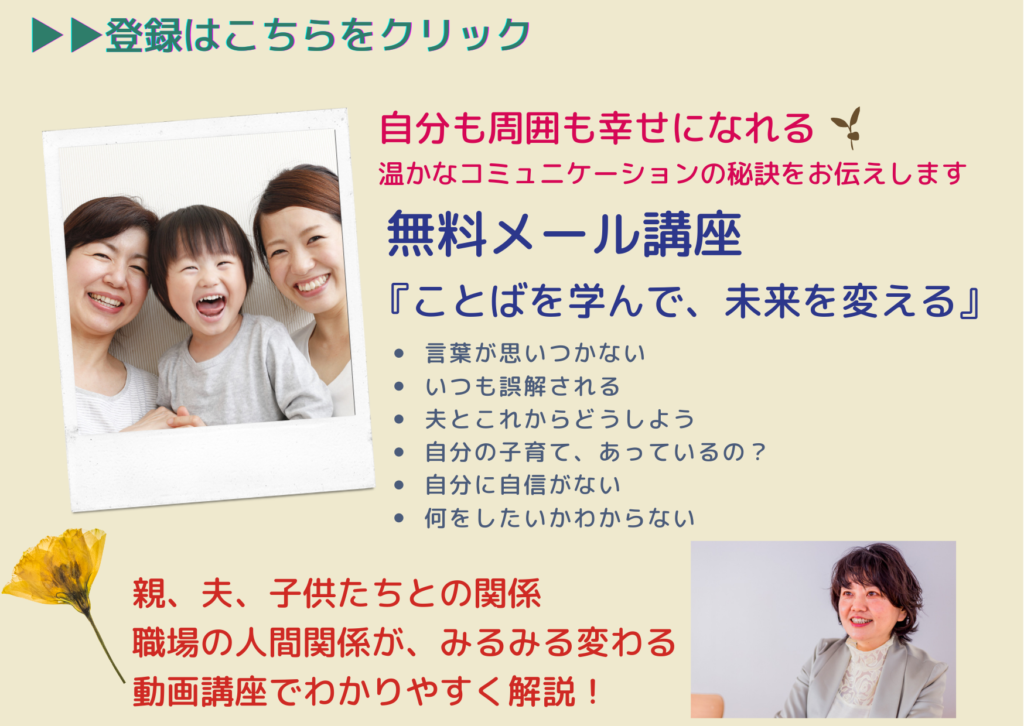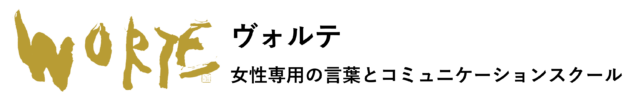言語造形からの贈り物08~お子さんに言葉の遅れ~
今回はお子さんにことばの遅れがあるケース、
音が出揃わないケースについてお話します。
発語の時期は様々です
お子さんが話し始める時期は様々です。個人差がとても大きいです。
1歳から話すお子さんもいれば、3歳まであまり離さないお子さんもいます。
音が出揃うのは5歳前後
けれども、日本語の中で育っている場合、
つまり、ご家庭の言葉が日本語で、幼稚園などの社会の言葉も日本語の場合、
日本語にある音がすべて発音できるようになるのは、遅くても5歳が目安です。
4歳で、遅れがある場合は、お子さんの様子を観察し、5歳になっても改善されない場合は
専門家と一緒のアプローチが望ましいです。
お子さんの発音は未分化
小さなお子さん、2歳頃までは、音が未分化の状態です。
とくに土の音(カ行、タ行、マ行、バ行、など)同士の言い間違い、
サ行のゆるさ、などが挙げられます。
たとえば、「台所(だいどころ)にあったの?」
これは小さなお子さんの場合、まだラ行とダ行が未分化で、
「らいろろろに」のように聞こえます。
これがきちんと「台所に」になるのが、5歳前後になります。
あれ、音が違うと思ったら
さて、お子さんがきちんと音が出せていないと思ったら、
どうすればいいのでしょうか?
まず、一番していただきたくないのが
「違うでしょ」と言い、「もう一回言ってごらん」など、間違いを注意することです。
音は聞き分けられているのか?
聴覚に問題があるのか、を観察してください。
ふだんのことばのやり取りで、気づくことができます。
話していて注意されると、どんな気持ちになるのか?
自分ではきちんと話しているつもりなのに、それを注意されるのは、
傷つきます。
正しく発音したくて話しているわけではありません。
言いたいこと、伝えたいことがあるので、話しているのですが、
それを受け取ってもらう前に、「違うでしょ」と押し返されることになり、
話したい気持ちが大きく傷つきます。
これが繰り返されると、話したい気持ちが外へ出られなくなり、
自分は話が苦手だと思ったり、自己評価が低くなったりします。
自己評価が低いことのほうが、一つ二つ音が上手に発音できないことよりも、
後々大きな影響を、その人のことばに与えます。
子どもにとってのことばのつまずき、対処は二つあります
まずご家族、ご両親ご自身の話し方を変えること。
ご自身は早口ではありませんか?
映像の浮かぶ話し方、イメージを描きながら話しをしていますか?
お子さんの話をゆっくり、じっくり聞いていますか?
お子さんにことばの栄養が行くように、お話ししていますか?
お子さんを注意するのではなく、自分の話し方を注意する。
もう一つはお子さん自身の運動能力、生活リズム、音が聞けているのかなどを
一つ一つ見ることです。
次回、どんな話し方、どんな声かけが、
お子さんにとってのごちそう、栄養になるのかをお伝えします。
言語造形人間学について
言語造形人間学は小野恵美のオリジナルの造語です。
シュ タイナー夫妻の始めたこと ばの芸術、言語造形を20年間実践し、ことばの音(子音、母音)と身体や動き、意識との関係、人間の成長との関係などを研究してきました。お話を教えるこ と、オリジナルの言語造形練習文を個人レッスンで各自に適応することで、その確実さを確認してきました。言語造形人間学は、シュタイナーの言語造形の精神 が結実したものです。ヴォルテのレッスンは、言語造形人間学に基づいて行われます。またヴォルテの上級クラスでは、集中講義としてその理論の講義を受ける ことができます。
まずは、
無料メール講座
『ことばを学んで、未来を変える』
で学んでみませんか?
無料でも、一切手抜きなしの内容です。
動画もたくさん入っていて、わかりやすいと評判です。
そして何より、すぐに日常生活に役立つものばかりです。
お申込みは下の写真をクリックしてください。