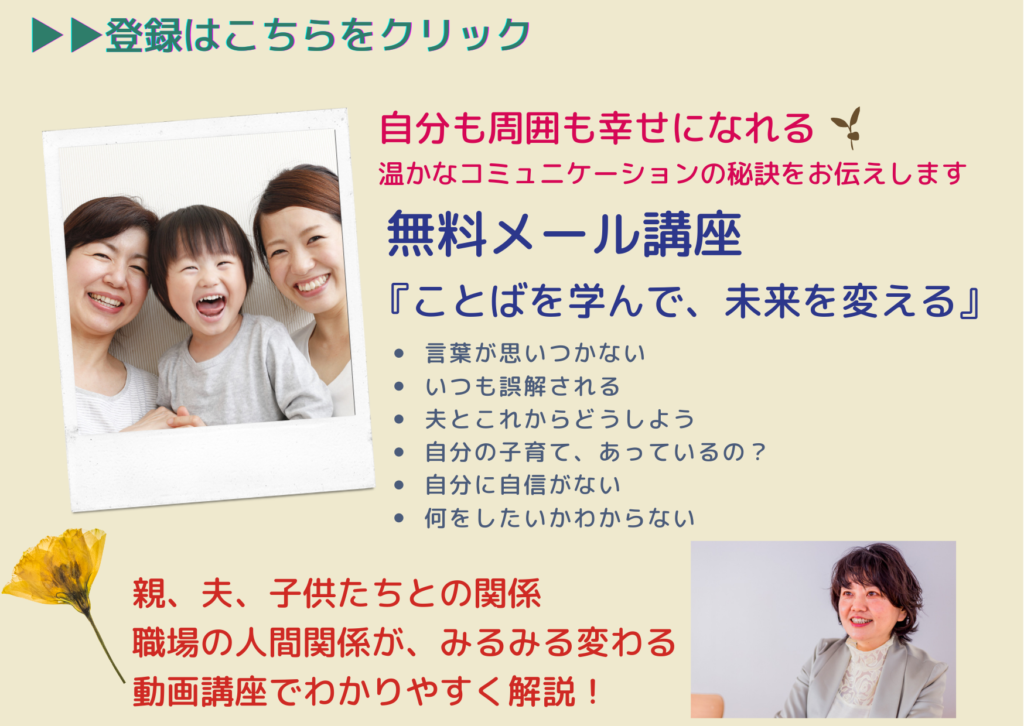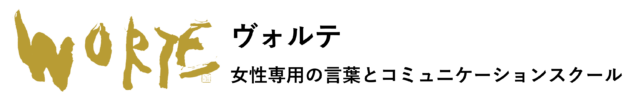言語造形からの贈り物09~周囲の大人の声かけ~
前回はお子さんに全ての音が出揃う目安について、お話しました。
今回は遅れがあるお子さんの周囲の大人の声かけについて、ご紹介します。
周囲の大人のことば、それが子どものことば環境
まず最初にお伝えしたいのが、周囲の大人たちの言葉こそが栄養だということです。
育っているお子さんにとって、自分のことばを得ていく際の大きな発育栄養なのです。
なかにはジャンクフードのような言葉のあり方があります。
いくつかの大事な点がありますので、本ブログでおいおい紹介していきたいと思います。
(WORTEのシリーズ講座『ことばは子どものごちそう』では、詳しくレッスンしています)
お母さんは大事だけれど
もちろん、基本的に常に一緒にいるお母さんの存在が大きいですが、
すべてをお母さんに押し付けるのはやめましょう。
それだけでとんでもないストレスがお母さんにかかります。
周囲が言わなくても、お母さんはお子さんに責任を感じており、
その度合いは部外者には想像がつかない深さです。
お父さん、保育園や幼稚園の教諭、おじいちゃんおばあちゃんなど、
周囲の大人の人たちがどんな風に話しているのかも、とても重要です。
声かけは二方向から考える
声かけで重要なのは、ことばの本質やコミュニケーションの本質と深く関わります。
一つ目は、自分が何を言いたいのか?
周囲の大人が子供にどう働きかけたいのかになります。
そして二つ目は、相手を聴くことです。相手を聴くことで生じることばです。
一番大事なことはしっかり聴くこと
言語造形の創始者の一人、マリー・シュタイナーはこんな事を言っています。
『私たちには口はひとつだけれど、耳は二つある』
話すことを学びたかったら、まずよく聴きなさいというのです。
聴く。それは人間関係においては、話を聴いている時に、自分が動いてしまうことです。
自分の意見も感情も、聴いている間は、一緒に動くことを意味します。
たいていは人の話を聞いているようで、
自分の聞きたいことだけをピックアップしているのが、現状ではないでしょうか?
そんな聴き方では、ことばは深まらない。
そんな厳しい言葉ですが、してみると、新しいことが見えてきます。
たとえば、気負わないですむので、双方の関係が柔らかくなり、信頼が深まります。
例
お子さんが車を指して、「るるま!」と嬉しそうに言ったとします。
お母さんやお父さん、園の先生はハッとします。
クルマってまた言えてない!!!
「違うでしょ、クルマでしょ。ク、ル、マ、って言ってみて!
はい、一緒に、ク、ル、マ!」
こちらとしては、日々の発語の中で稽古しているつもりかもしれませんが、上記はよくない例です。
発語する気持ちを萎えさせていきます。
車が好きで車を見たので、嬉しくなって指を指して、そばにいる信頼している人に
「車がいたよ!嬉しいな」と伝えたかった。
お子さんはクルマと正しく発音したいがために、発語したわけではないのに
直されてしまった。
すると自分から相手へ差し出したものが、拒まれ、理解されなかったことが心に残ります。
このようなことが周囲にいる大人全員によって繰り返されると、発語したい気持ちが
どんどん傷つけられていきます。そしてそんな自分自身に、自信を失っていきます。
もちろん、子供なので自信がないとは自覚できないかもしれませんが、
それは様々な症状へ数年かけて発展していく恐れがあります。
これからその子が、学校、社会へと出て行き、
親がいない場所でも生きていくことを考えると、
発語する気持ちをまずは育てていくことのほうが、正しい音よりも重要ではないでしょうか。
あまり話さなくなる。
あるいは全く話さなくなる。
自分への信頼を損なってしまうが、そのことには気づかないまま大人になる。
その結果、「本当は自分はすごいんだ」などの歪んだ自尊心を持つ人になり、
例えば、スキあらばクレームを激しく言う人になったり、自慢をやめられない人になったり、
人間関係上、素敵ではない様々な傾向を帯びていく種になります。
ではどうすればいいのか?
お子さんがなぜ発語したのか、その気持ちを感じるようにしましょう。
正しい音かどうか、は、発語する気持ちから見ると、重要なことではありません。
「くるまだね、嬉しいんだね」
「ほんとだね、くるまだね、うちのと同じだね」
するとお子さんは嬉しくなり、話すことを続けていくでしょう。
ぜひ、なさってみてください。
「くるまだね」と、大人の方は正しい音を発語しているので、
これだけで音の栄養はお子さんに入っています。
もしもこのような通常の声かけで、お子さんが5歳を過ぎても音が言えない場合は、
やはり特別なケアが必要なのかもしれないと判断していく材料になります。
ことばの要素には、前回と重なりますが、
音があるだけではなく、発語する動機があることをお伝えしました。
次回はそのほかのことばの要素について、お伝えします。
言語造形人間学について
言語造形人間学は小野恵美のオリジナルの造語です。
シュ タイナー夫妻の始めたこと ばの芸術、言語造形を20年間実践し、ことばの音(子音、母音)と身体や動き、意識との関係、人間の成長との関係などを研究してきました。お話を教えるこ と、オリジナルの言語造形練習文を個人レッスンで各自に適応することで、その確実さを確認してきました。言語造形人間学は、シュタイナーの言語造形の精神 が結実したものです。ヴォルテのレッスンは、言語造形人間学に基づいて行われます。またヴォルテの上級クラスでは、集中講義としてその理論の講義を受ける ことができます。
まずは、
無料メール講座
『ことばを学んで、未来を変える』
で学んでみませんか?
無料でも、一切手抜きなしの内容です。
動画もたくさん入っていて、わかりやすいと評判です。
そして何より、すぐに日常生活に役立つものばかりです。
お申込みは下の写真をクリックしてください。