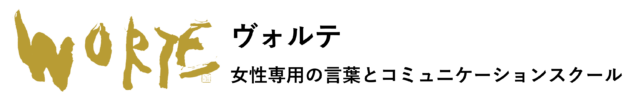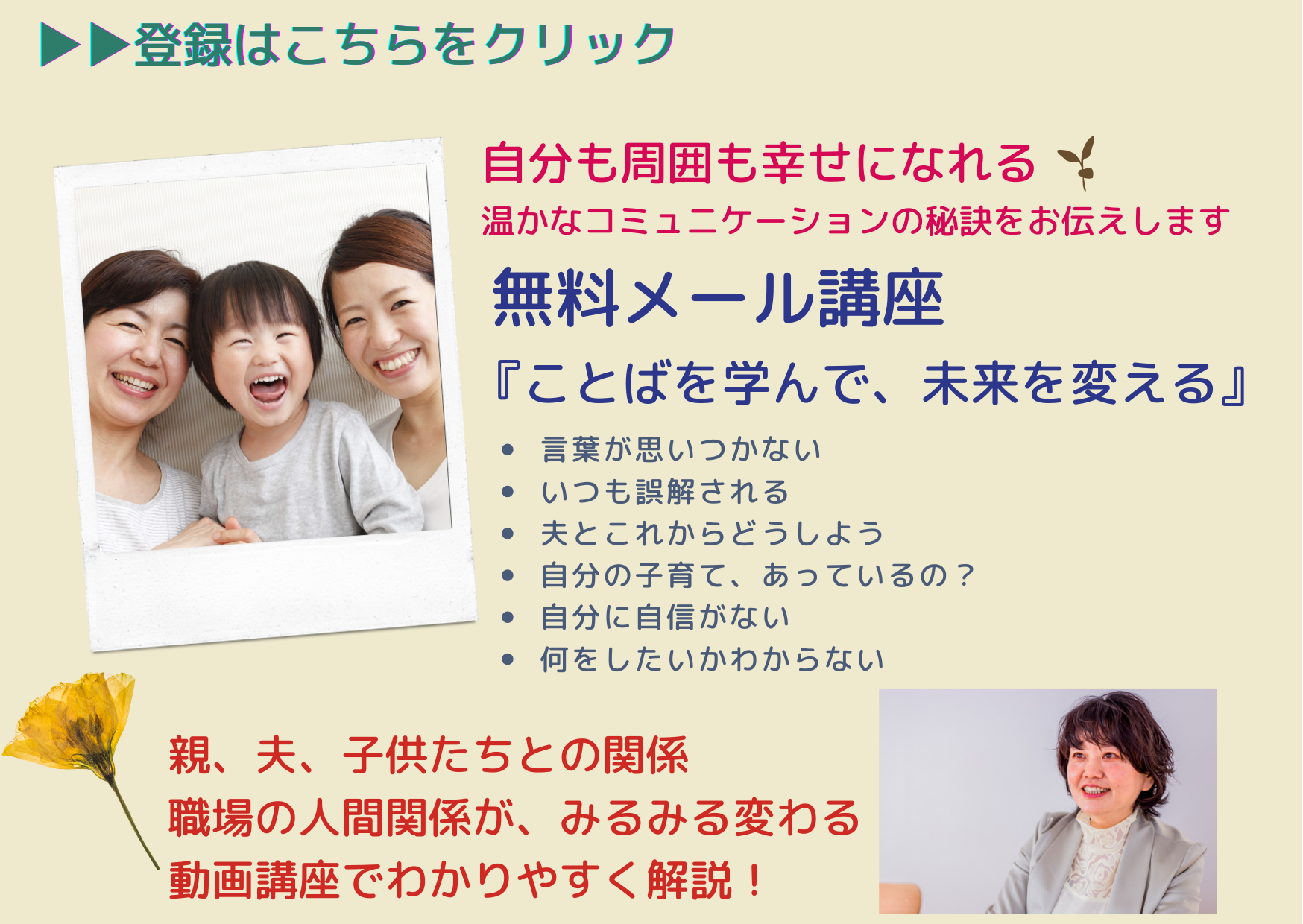言語造形人間学 空間のアンバランス 得意な方向、苦手な方向
今週はワークショップがありました。
言語造形練習文で、お一人ずつのことばの身体マップを書く。
そんなワークショップでした。
音でわかる、その人のことばの身体
母音、子音をどんな風に発音するのか、
その時の重心、手足の動き、力の入れ方、
音の響き、声の変化で、様々なことがわかります。
身体がわかるだけで、その人そのものがわかるわけではありません。
それは医師や治療家が患者の身体がわかるけれど、
その人そのものが全部わかるわけではないのと同じです。
人によって、得意な空間、そして忘れている空間、
苦手で避けている空間、無意識に避けている空間、
などがあることを実感しました。
前が強いと、後ろが弱くなりやすい
たとえば前に前に出て行く人もいます。
そういう人はたいてい後ろの空間があることを
忘れています。
右と左のバランス
右側ばかり使う方は、左側、そして心臓があることを
忘れがちです。
右側の世界は働きかける、効率のよい世界です。
左側は人と一緒にいる、感じる世界です。
どちらかだけになると、アンバランスになってしまい、
周囲の方もしんどいし、ご本人もしんどくなってきます。
上と下のバランス
上の空間ばかりで、重心が下へ下がる動きをしない方もいます。
重心の変化は、声の上下に現れやすいです。
声がうわずる、という表現があるように、
声の上下は、話している人の心理を表すことがあります。
弱い空間に身を置くことで、力をもらおう
こんな風に、ひとつひとつの空間には特徴があります。
前に行きがちな人は、
後ろの背もたれにゆったりと身を預けるだけで
気分が違ってきます。
アンバランスの理由はいろいろ
前の空間にばかりいる方。
自分がいなければ何も始まらないと
どこかで思っていたかもしれません。
あるいは誰も手伝ってくれない生活に疲れているかもしれません。
なんにでも首をつっこむタイプなのかもしれません。
そんな方は、ゆったり人の話に耳を傾けられるようになれば、
鬼に金棒。
どんな理由にせよ、前ばかりになると
普段不足しがちになっているのが、後ろの空間です。
アンバランスを感じましょう
こんなふうに個性が現れる空間性ですが、
面白いことに、年代で共通する空間があります。
小さな子供、お年寄りは、どうしても後ろの空間が強いです。
小さな子供は上、お年寄りは下、など、
違いもあります。
今日は連休最後ですが、
前後
左右
上下
の中で、
ふだんあまり気づかない場所があるか、振り返ってみてください。
よい週末を!
無料メール講座
『ことばを学んで、未来を変える』
で学んでみませんか?
無料でも、一切手抜きなしの内容です。
動画もたくさん入っていて、わかりやすいと評判です。
そして何より、すぐに日常生活に役立つものばかりです。
お申込みは下の写真をクリックしてください。