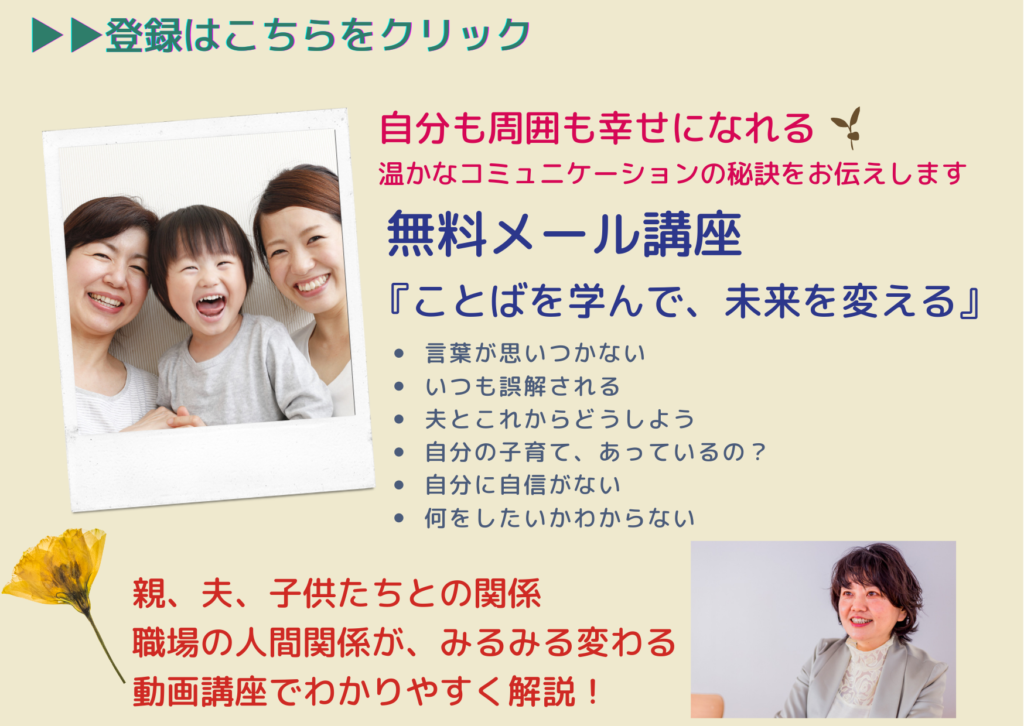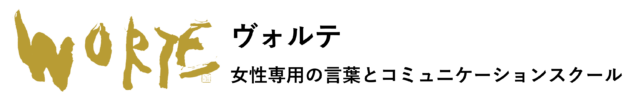言語造形からの贈り物06~ことばのつまずき、吃音について~
今回も引き続き、ことばのつまずきについてです。
吃音を取り上げます。
吃音について
どの音で吃音になるかは、その人によって違いますし、状況によっても違います。
シュタイナーは吃音を「器官化した不安」と言っています。
あまり意識していませんが、話すとき私たちは息を吐いています。
けれども、吸いながら話す、これを織り交ぜると、吃音になります。
試しになさってみると、ご理解いただけると思います。
器官化とは?
不安があるので、息がなくなってしまう前に、息を吸う。
それが吃音の原因である。
そう述べています。
器官化した、つまり、胃や腸のような器官になった不安ですから、
大人が吃音と取り組むのは、ある意味で胃や腸の働きを変えるようなことに当たります。
大人が直すには非常な根気が必要となります。
シュタイナーは吃音について、どう話しているのでしょうか?
少し長いですが紹介します。
『話しているとき、まだ息が残っているのに、息を吸う。これが吃音の原因です。
吃音者は、いわば器官化した不安を持っていて、そのために息を吸おうとするのです。
吃音が始まったら、吃音者に「歌うか、詩にして」というのです。
これからするお話はみなさんもご存知かもしれません。
ある薬局の薬剤師に、吃音のある男がおりました。5時のお茶のとき、「やっ、やっ」と話し始めました。でもか行が出てきません。しかし彼が必死なので、周りの人が「言いたいことを歌って!」と言うと、「薬局が火事だ~。すぐに地下室へ行かねばならない~そこがひどく燃えている~」と歌ったのです。歌うと、吃音は出ないのです。
けれども訓練によって、吃音を治そうとするなら、地道に時間をかけなければなりませんし、
練習にかける内的なエネルギーも要求されます。しかも器官化した不安ですから、無意識に吃音が出てくることが稽古をしても出てきます。
吃音に関して、私の友人で詩人がおりました。彼は吃音者でしたが、彼は自分の詩を、リズムに乗せ、長い長い行を、吃音の気配を感じさせることなく、朗読していました。けれども普通の会話になると吃音が始まりました。友人には吃音を治す訓練を根気よく続ける粘りがなかったのです。
あるとき、あまり礼儀をわきまえない人にこう聞かれました。
「博士、いつもそんなに吃音があるのですか?」
すると友人はこう答えたのです。
「と、と、と、とても、い、い、いやな人を目、目、目の前にするとき、だ、だ、だけです」』
(ドラマコースシュタイナー全集282より、抜粋 小野恵美私訳)
あってもいいのでは?吃音
18歳の時から言語造形に関わって、26年になりますが、
私はこれを読むたびに、なるほどなあと思います。
本人がここまで分かっているのなら、別に吃音があってもいいのでは?と。
ユーモアがありますし、そういう類の質問をする人は吃音じゃなくても、
いろいろなことを聞いてきます。それに対して、こんなふうに返事ができるなら、
生きていくには十二分です。
といはえ、吃音に効果のある音がありますし、お子さんの場合はいろいろ異なってきますので、
次回、ご紹介します。
言語造形人間学について
言語造形人間学は小野恵美のオリジナルの造語です。
シュ タイナー夫妻の始めたこと ばの芸術、言語造形を20年間実践し、ことばの音(子音、母音)と身体や動き、意識との関係、人間の成長との関係などを研究してきました。お話を教えるこ と、オリジナルの言語造形練習文を個人レッスンで各自に適応することで、その確実さを確認してきました。言語造形人間学は、シュタイナーの言語造形の精神 が結実したものです。ヴォルテのレッスンは、言語造形人間学に基づいて行われます。またヴォルテの上級クラスでは、集中講義としてその理論の講義を受ける ことができます。
まずは、
無料メール講座
『ことばを学んで、未来を変える』
で学んでみませんか?
無料でも、一切手抜きなしの内容です。
動画もたくさん入っていて、わかりやすいと評判です。
そして何より、すぐに日常生活に役立つものばかりです。
お申込みは下の写真をクリックしてください。