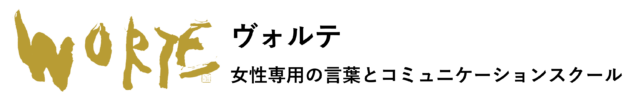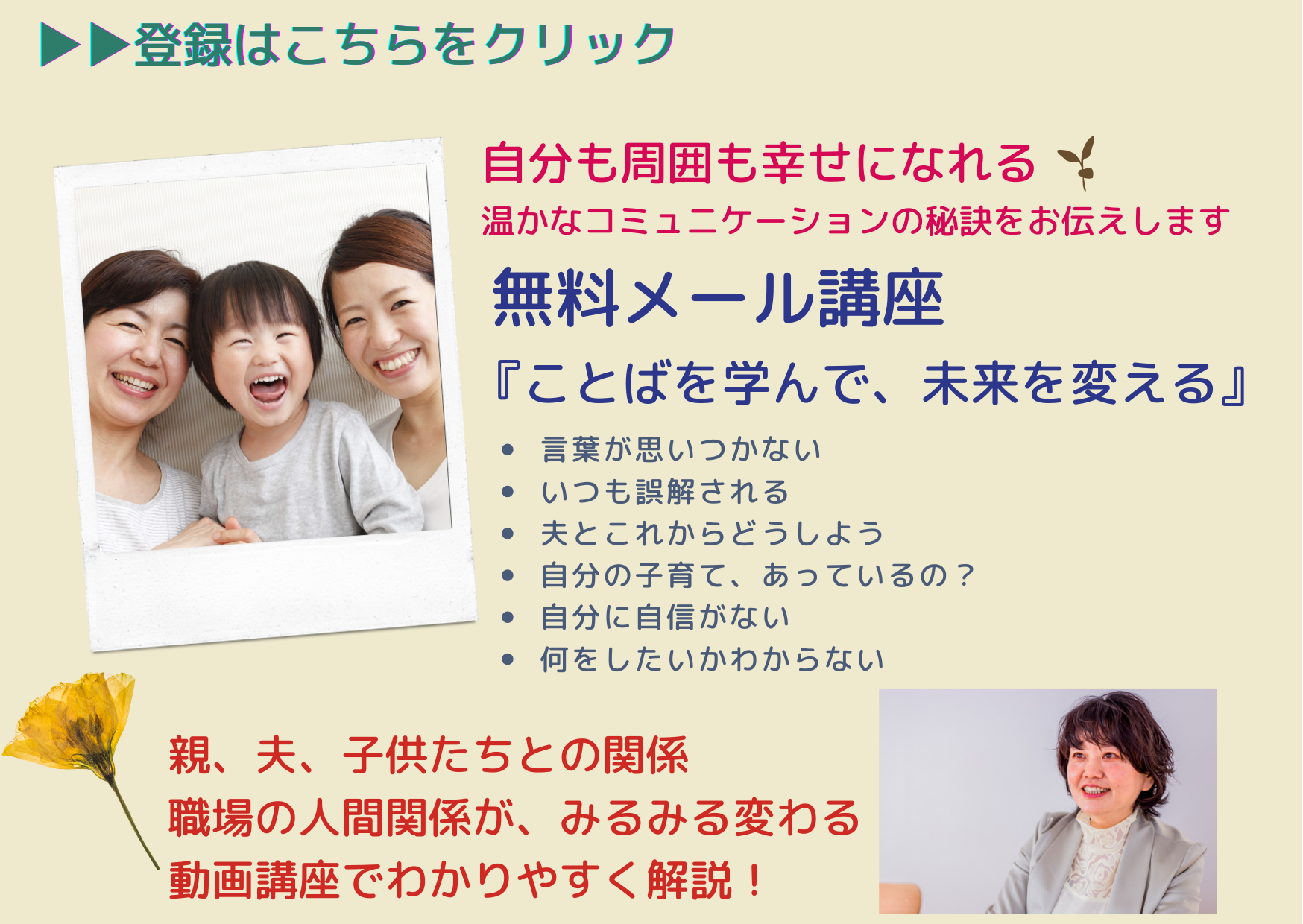日常はワンダーランド 小話のレッスン7
先週はライブのため、お休みをいただきました。
さて、前回は50年前のことをお話くださった例をご紹介しました。
50年前の小学校のお友達、恵子ちゃんとの冒険、橋を渡って、
竹林の中でおままごとをした話しでした。
最後のオチは、同じ場所へ橋を渡って出かけてみたら、
竹林がなくなって、野球場になっていたこと。恵子ちゃんどうしているかなあ、と思ったことでした。
年月だけが生み出す手触り
不思議な手触りの小話でした。
50年間、語り手の中に存在していた。
だからこそ生じる手触り、雰囲気がありました。
深みやスケールがほんわりとしていて、
聞いているだけでとっても面白かったです。
この面白さは推理小説で犯人を追いかけたり、
謎解きをするような面白さの、まさに対局にあるものでした。
ただそこにあるだけで面白い。
タイムトラベル
私たちは思い出すこと、
そして未来を可能性を思い描くことで、
まさにタイムトラベルをしているんじゃないか。
そしてまた現在とつながること。
そのようなことをたまにすることって、大切なことなのです。
というのも、ここからが本日の本題ですが、
シュタイナーがよく例にあげるエピソードがあります。
自我は記憶の関連と関わる
それは自我が記憶と関係があるという話しなのです。
ふだんは記憶はエーテル体と言っているのですが、ここではそうではありません。
シュタイナーがあげている例なので、もう100年くらい前のことですが、
こういことが始まりつつあるよと前置きをして、ある大学教授の例をあげています。
その人はヨーロッパで行方不明になり、何年も発見されませんでした。
切符を買って列車で旅行に行くはずだったのですが、
そのまま行方がわからなくなりました。
自分が誰なのか、何をしようとしているのか、すっかり忘れてしまって、
切符を持ってドイツの人なのに北欧あたりをウロウロしていたという人の例でした。
つかむこと、それが生きていること
この人の例をシュタイナーは何回も、異なる講演の中で取り上げてます。
つかむことができなくなる。
自我が弱くなることで、私たちは関連をつかめなくなるのだ、と。
私は今実際に、痴呆の初期症状が出ている家族がおりますが、
つかめなくなっていると、感じます。
もう物事をつかめない。
だから何度も同じことを尋ねる。
もう体をつかめない。
だから転んでしまう。
シュタイナーは神智学(テオゾフィ)という著作の中で、
死を肉体が魂をそっと手放す、と述べています。
私にはまだよくわからないのですが、
魂が肉体を手放す、のではないようです。
関連がわからなくなり、痴呆が出てくることを
自我が弱くなることの症状としてシュタイナーは
述べていたのかもしれません。
関連とは、この小話のように、小学校の時のお友達を思い出し、
その場所へ行ってみて、その人はどうしてるかなあ?と思うことです。
そして可能ならば、その話をしてみることです。
聞き手がいてくれるとき、私たちの行為は
思い描いているだけの時とは、また別のリアリティを得ることができます。
それにしても小話でタイムトラベルも可能だなんて、
まさに日常はワンダーランドです!
みなさんも10歳ごろのこと、7歳頃のこと、
何か思い出して小話にしてみてください。
タイムトラベル、できると思います。
そして思い出したもののオチにみなさんが何を言うのか。
お一人ずつ、全然違うものになるはずです。
それがまさにみなさんの自我の表れなんですよね。
シュタイナーの勉強会や講演で自我自我ってよく聞くと思いますが、
じゃあ、具体的になんなのか?やってみようよ!
ということを、WORTEでは大事にしています。
寒暖の差が激しいですが、
体調にお気をつけくださいませ!
言語造形人間学について
言語造形人間学は小野恵美のオリジナルの造語です。
シュ タイナー夫妻の始めたこと ばの芸術、言語造形を20年間実践し、ことばの音(子音、母音)と身体や動き、意識との関係、人間の成長との関係などを研究してきました。お話を教えるこ と、オリジナルの言語造形練習文を個人レッスンで各自に適応することで、その確実さを確認してきました。言語造形人間学は、シュタイナーの言語造形の精神 が結実したものです。ヴォルテのレッスンは、言語造形人間学に基づいて行われます。またヴォルテの上級クラスでは、集中講義としてその理論の講義を受ける ことができます。
無料メール講座
ことばを学んで、未来を変える
で学んでみませんか?
無料でも、一切手抜きなしの内容です。
動画もたくさん入っていて、わかりやすいと評判です。
そして何より、すぐに日常生活に役立つものばかりです。
お申込みは下の写真をクリックしてください。